
ヒラマサには寄生虫がいることがあるって聞いたけど、実際のところどうなの?
どうも平政男です。
ヒラマサは食べると本当に美味しいですが、よく心配されているのが寄生虫の存在ですよね。
もし生きた寄生虫がついたヒラマサを食らおうものなら、胃や腸が張り裂けそうになるくらい痛くなると言われています、、。
あなたはそんなふうには絶対なりたくないですよね?
ということで今回は、ヒラマサに寄生虫はそもそもいるのか、いたときの寄生虫の対処法についてお伝えしていきます!
ヒラマサに寄生虫はいる
結論から言うと、ヒラマサに寄生中がいることは良くあります。
ヒラマサに限らず、同種のブリやカンパチなどの青物は特に寄生虫が宿りやすいので注意が必要です。
ではどのような寄生虫がヒラマサにはついているのか、それらの対処法などについて以下で詳しく解説します。
ヒラマサに寄生する寄生虫の種類
ヒラマサには以下の種類の寄生虫がついていることがあります。
- アニサキス
- ブリ糸状線虫
- 粘液胞子虫類
- テンタラクリア
- シガテラ毒
アニサキス
ヒラマサを食べるときに最も気を付けたい寄生虫がこのアニサキスです。
生きた状態のアニサキスを誤って食べてしまうと、人間の胃や腸の壁に付着して激しい痛みや嘔吐下痢などを引き起こします。
基本的にアニサキスはヒラマサの内臓に寄生していることがほとんどなので、内臓をしっかり除去したり、内臓付近の筋肉や血合いをよく水洗いして確認するようにしましょう。
ブリ糸状線虫
ブリ糸状線虫は名前の通りブリに多く寄生していますが、ヒラマサも例外ではありません。
とはいえこの寄生虫は食べても害がでることはありません。
またブリ糸状線虫は養殖では寄生しないので、もしブリ糸状線虫が見つかったら天然ヒラマサです。
粘液胞子虫類
粘液胞子虫類はヒラマサの筋肉や内臓につく寄生虫で、米粒状の形をしています。
これといった毒性は現在解明されていませんが、下痢や軽い嘔吐を引き起こしたという症状も確認されているそうです。
もしヒラマサの身に米粒状のものを見つけたら、取り除いておきましょう。
テンタラクリア
テンタラクリアは粘液胞子虫類と同じく米粒状の形をしており、ヒラマサの筋肉や内臓に寄生します。
誤って口にしてもアニサキスのような辛い症状は確認されていないが、やはり見つけた時には取り除いておくのが無難でしょう。
シガテラ毒
こちらは番外編。
シガテラ毒は寄生虫ではありませんが危険な神経毒であり、ヒラマサが持っている可能性もあります。
特に大型の個体や亜熱帯~熱帯地域に生息しているヒラマサは持っている可能性が高いです。
致死率は低い毒ですが、神経障害や胃腸障害、舌や手足のしびれ、嘔吐下痢、温度を上手く感じられなくなるなど、日常生活に支障をきたすレベルの害があります。
ヒラマサについた寄生虫の対処法
ここまでヒラマサにつく寄生虫の種類について解説しましたが、ヒラマサについた寄生虫を対処するにはどうすればいいのか。
その中でも特に症状が酷いアニサキスの対処法について今回は解説しましょう。
ヒラマサについたアニサキスは以下の方法で対処します。
- 完全に除去する
- 加熱処理する
完全に除去する
アニサキスは完全にヒラマサの体内から除去することで症状を予防できます。
一般的には内臓や血合い付近についている可能性が高いアニサキスですが、ヒラマサの鮮度が落ちるにしたがって内臓から筋肉へと移動をする習性があります。
内臓と血合いを確かめたから大丈夫と思っていると、筋肉に付着したアニサキスを見逃してしまうので気を付けましょう。
ちなみにアニサキスは目視できるサイズ(2~3cm)なので、捌いていれば自然と見つけられるはずです。
加熱処理する
アニサキスへの対処法のもう一つに加熱処理があります。
万が一アニサキスを除去しきれていなかったときも、加熱処理をすればアニサキスを死滅させられます。
加熱処理の際は、60℃で1分以上、もしくは70℃以上で加熱すれば大丈夫です。

確実に安全に食べたいなら刺身じゃなく加熱調理して食べるのがおすすめです。
ヒラマサを刺身で食べるときの注意点
もしヒラマサを刺身で食べるときがあれば、必ず以下のことに注意しましょう。
- 内臓を取り切る
- 血合いをよく掃除する
- 身をよく観察する
内臓を取り切る
ヒラマサに寄生する多くの寄生虫は内臓に付着することが多いです。
捌くときは必ず内臓を綺麗に除去するように心がけましょう。

綿袋や血合い周りの透明な筋膜もしっかり剥がしておくように。
血合いをよく掃除する
内臓を綺麗に取り除いた後は血合いをよく掃除しましょう。
内臓を除去したとしても、寄生虫は内臓から血合い付近まで移動している可能性が十分あります。
血合いにある固まった血は手だけでは完全に落としきれないので、包丁の先端を使って除去しましょう。
身をよく観察する
内臓を取って血合いをよく掃除したあとは、身をよく観察しましょう。
身は食する部分なので、内臓や血合いよりもより入念に確認しましょう。
2~3cmの線状のものが付着していたらアニサキスなので、こちらは必ず取り除いてください。
また表面ではなく身の中にめり込んでいる可能性もあるので、骨抜きやピンセットなどを使って確認するとより確実です。
また以下の動画でヒラマサの正しい捌き方について解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
ヒラマサは寄生虫に気を付けて食べよう
今回はヒラマサについている寄生虫について解説しました。
色々な種類の寄生虫がいますが、特に気を付けるべき寄生虫はアニサキスです。
アニサキスは症状が非常に重たく、私生活にまで支障をきたします。
寄生虫をしっかり対処して、ヒラマサを美味しく食してくださいね(^^)/
今回は以上です。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
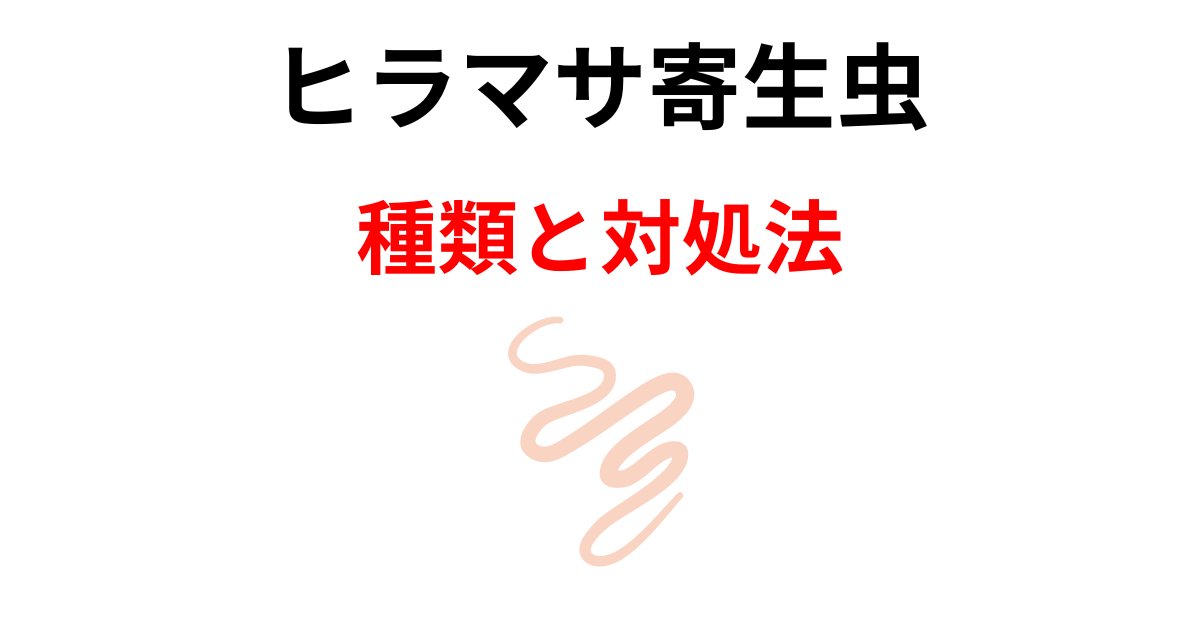
コメント